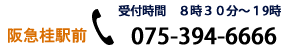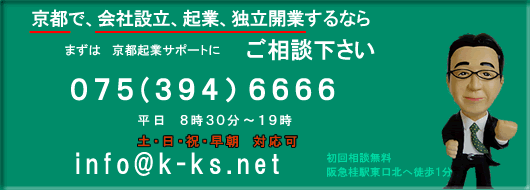- HOME
- >
- 会社設立
会社設立か個人事業か
許認可が伴う場合や規模が大きい場合は、会社設立
平成18年5月1日施行の会社法の下では、一般的に会社設立して起業することが多くなったといわれています。
では、個人として起業するのと会社を設立して起業するのではどんな違いがあるのでしょう?
一般的には、代表者一人や家族で小規模に起業する場合には個人事業、比較的短期間に大きな事業展開を考えられる場合には会社を設立する傾向にあるようです。
建設業等比較的大きなお金が動く場合や、大きな信用が必要な業種で起業する場合、会社設立がお薦めです。後に、資金不足が生じ、他から資金調達が必要となった場合、増資手続きを経て株主となってもらう方が、個人事業主が貸付により資金援助を受けるより、援助する側にとって協力しやすいからです。
また、当初個人事業として起業し、後に法人成しようとした時に、面倒となることがあります。
たとえば、許認可がいる建設業や派遣事業のような業種の場合、登記上会社組織にしたからといって、いままで個人事業主として取得していた許認可が自動的に引き継げることにはならない点が、やっかいなところです。許認可を取り直す場合が多いのが現実です。
コスト面でも、個人事業主から法人に成ると、看板や名刺等多くのものを一から作り直さないといけないので、その点でもデメリットといえるでしょう。
そのようなことが考えられる業種であれば、はじめから会社組織にして起業した方がいいかもしれません。
いずれにせよ、複雑で専門的な手続きが伴う会社組織の場合、司法書士や行政書士、税理士、社会保険労務士がワンストップで対応してもらえるところを探すのが賢明です。
会社設立のメリット
1.税法上の特典が多い
2.外形上、信用力がある
3.求人確保がしやすい
4.契約するうえでの条件 (フランチャイズ契約や得意先との契約)
5.助成金が得られる範囲が広い
6.代表者が死亡しても会社法人格は存続(個人の相続とならない)
7.社会保険に加入できる
8.決算期が選択できる
9.経費の適用範囲が広い
10.資金調達がしやすい
個人事業のメリット
1.税務署への届出だけで、すぐに開業できる
2.会社設立するような登記費用や社会保険新規適用手続き等が不要
3.複雑な手続きに時間が取られず、開業準備に時間を使える
4.開業当初、資本金等のまとまった資金がいらない
5.会社のように当初から事業目的を定款に厳格に規定する必要がない
6.会社法人のような複雑な複式簿記や法人税の申告手続きがいらない
7.事業をやめる場合も、債務があるような場合を除き、比較的簡単
会社の種類
株式会社・合同会社・合名会社・合資会社・有限会社
現在ある会社には、株式会社、合同会社、合名会社、合資会社及び有限会があります。その中の、有限会社は、旧商法時の会社で、現在は新規設立することはできず、以前作られた有限会社が、特例有限会社として存続しているにすぎません。
合名会社と合資会社は、無限責任を伴う社員がいるもので、現在、新規で設立されることはほとんどありません。
また、一般社団法人や有限責任事業組合(LLP)は、いわゆる「会社」ではありません。
よって、現実には、新規で会社を設立する場合、株式会社か合同会社になります。
株式会社か合同会社か
株式会社と合同会社の比較
株式会社と合同会社は、構成員・損益分配・設立費用や、役員任期・決算公告の有無、等に違いはありますが、出資者が有限責任である点や、税法上メリットがある点に変わりはありません。
現在、当サイトにて会社を設立する方の場合、ほとんどが株式会社で、合同会社は比較的少ないのですが、その理由を考えると、当サイトで起業される方は、サラリーマンから背水の陣で独立創業を志し、将来自社を長く、大きく、成長させたいと真剣に考える方が多いからかもしれません。
株式会社に比べ、認知度が低い合同会社を敢えて選ばれる方は、「税法上の特典が同じなら、低コストで設立できる方を選ぼう。」という、堅実で現実的な方が多いようです。既に別会社を持っていたり、サラリーマンの方が資産管理会社として立ち上げる際に、合同会社を選択する事例は増えつつあります。以下、表にて比較しておきます。
| 株式会社・合同会社の比較 | 株式会社 | 合同会社 |
| 登録免許税 | 150,000円 | 60,000円 |
| 定款認証費用 | 54,000円 | 不要 |
| 出資者の責任 | 有限 | 有限 |
| 税法上のメリット | あり | あり |
| 役員任期 | 最長10年 | なし |
| 損益分配比 | 出資額按分 | 自由 |
| 決算公告 | 必要 | 不要 |
会社設立の専門家とは
会社を設立すると、今まで聞いたこともない多くの専門家(士業)がかかわることになり、どの士業がどんなことをやってくれるのかわからない方が多いようです。
そこで、会社を設立して、経営していくうえで、以後かかわりそうな士業専門家を挙げ、その仕事を説明しておきます。
司法書士
会社法や商法、商業登記法等の会社法律科目を試験問題とした合格率2%の難関試験に合格した、会社設立の専門家です。
その業務は、会社設立当初の定款作成、定款認証、設立関係書類の作成、設立登記の代理申請など幅広く、会社設立手続きの全てを司法書士だけで行うことができます。
会社は、法務局に申請して登記されないと会社として成立しない(登記が効力要件)ので、登記ができる専門家(司法書士)が運営しているサイトかどうかが、会社設立を依頼するサイトを選ぶ基準と言ってもいいかもしれません。
会社設立後も、役員や本店、目的に変更が生じた場合、変更登記を申請したり、それら書類作成する専門家も司法書士になります。
当サイト代表は司法書士であり、最近の悩みは、専門分野でない他士が作成した定款で、後日変更登記をする際、不満を感じることが多くある点です。定款は会社法をしっかりと理解した専門家が作成するべきで、定款作成される方は、後日の変更登記に支障がないものを作っていただきたいと考えています。
行政書士
主に会社設立後に、府庁や市役所等の官庁に提出する書類を作成し、許可・認可・登録・届出(以下「許認可手続き」という。)などの代理申請を行う専門家です。
建設業や宅建業で会社を設立して起業した場合には、許認可手続きが必要となります。
行政書士さんも定款作成をすることができますので、定款認証手続きも代理できますが、登記は司法書士に別途依頼しないといけないので、トータルコストは別途司法書士の報酬も加味して考えないと、かえってコスト高になることがあるので、注意が必要です。
税理士
会社設立後、三官庁(国税・府税・市税)に開業届等を提出し、以後、会社の顧問となり、帳簿作成や税金についてのアドバイスを行い、毎年期末後2ヶ月以内に法人税の申告を代理申請する、税の専門家です。
最近では、税理士さんが行政書士登録をした上で、低額で会社設立を代行(登記はできません)するようなサイトも出てきましたが、それらは顧問契約を得るために行っているもので、安易に依頼すると、相性のよくない税理士さんと長くつきあうことになるかもしれないので、安い理由をよく考えた上で、依頼先を決めることをお勧めします。
良し悪しは別にして、決算料だけで月々の顧問料を必要としない税理士さんもいるようなので、その場合、会社設立を月々顧問料のいるサイトに依頼すると、設立後すぐに顧問料が出ていくことになるので、注意が必要です。
社会保険労務士
会社設立後、社会保険(健康保険・厚生年金保険・介護保険)と労働保険(労災保険・雇用保険)の手続きを代理申請する専門家です。
また、最近では、介護保険法に基づく訪問介護・訪問看護手続きや、労働者派遣手続きをされる社労士さんも出てきました。